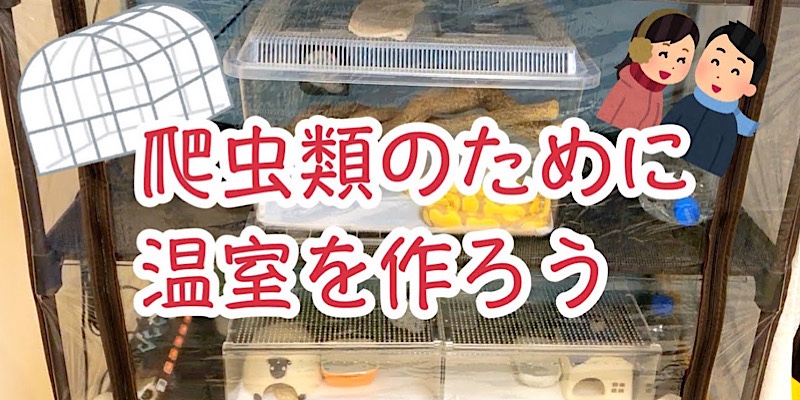みんな大好きレオパの飼い方を紹介します。
初めて飼育される方に向けて、ヒョウモントカゲモドキの特徴と種類・食べる餌・必要な飼育用品を解説していきます。
目次
レオパの特徴
レオパ(和名:ヒョウモントカゲモドキ)はアフガニスタン南部に生息するヤモリで、名前の通りヒョウ柄の斑点が特徴です。
英名のレオパードゲッコーから「レオパ」と呼ばれます。
体長と体重
個体差はありますが、アダルト(成体)になると、体長は約25cm前後、体重は50gから80gになります。
中には100gを超える個体や、「ジャイアント」と呼ばれる身体の大きなモルフも存在します。
寿命
飼育下のレオパ(ヒョウモントカゲモドキ)は、約10年から15年もの間、生きることがあります。
最期まで飼育を全うできるかどうか、しっかりと考えてお迎えしましょう。
生き物のため、生後すぐに弱ってしまう場合や、数年で亡くなってしまう個体もいます。
温度と湿度
レオパを飼育するため、温度は28〜32度、湿度は40〜60%が必要です。
日本では爬虫類用のヒーター、エアコンでの温度調整が必要となります。
真夏の直射日光には注意して、日陰にケージを設置しましょう。レオパは夜行性のヤモリのため、紫外線は必要ありません。
真冬に暖まりきらない場合は、断熱材でケージを囲うなどの防寒対策を行って下さい。
レオパの種類
世界中のブリーダーによって、レオパも品種改良されています。柄や模様、体色の確立した品種をモルフと呼びます。
モルフ同士の掛け合わせによるコンボモルフがあり、数え切れない種類が存在します。
ハイイエロー

最も一般的なモルフで、ノーマルと呼ばれることもあります。
ワイルド(野生)の黄色みの強い個体同士を選別交配させて、作出されました。
値段も安く、初めてレオパを飼育する初心者さんに人気です。
スーパーマックスノー

数あるモルフの中でも一二を争う人気を持つスーパーマックスノー。
真っ黒なつぶらな瞳と、マックスノーの特徴である黄色い色素が抜けた、黒と白のコントラストが目立つ背中が特徴です。
マックスノー同士を交配させると生まれてくるモルフです。
タンジェリン

名前のとおり蜜柑のような、オレンジ・赤の強い色味をもつモルフです。
タンジェリンは、世界中のブリーダーが独自の選別交配を行っており、数多くのラインが存在します。
身体だけでなく、尻尾までオレンジに染まっている個体をキャロットテールと呼びます。
アルビノ

アルビノは、メラニン色素を作れない体質のため、身体や目から黒色が抑えられます。
写真の個体は、スーパーマックスノーとアルビノ、そしてエクリプスが入っているため、身体が白く、真っ赤な目を持ちます。
アルビノの遺伝子を持つレオパは、視力が弱い傾向にあり、他のモルフより食べるのが下手な個体がいるので、ピンセットでの餌やりが必要な場合もあります。
レオパのアルビノには「ベルアルビノ」「トレンパーアルビノ」「レインウォーターアルビノ」の3種類が存在します。
レオパの餌
レオパは、コオロギやクモ・サソリなどを食べる「昆虫食」です。
飼育下では、冷凍コオロギ・乾燥コオロギをピンセットで摘み、揺らして興味を誘うことで食いつかせることもできます。
コオロギ
適度に動き回る為、置きエサとしても優秀です。ゴキバンクでも、レオパの飼育ケージにコオロギを数匹いれておくこともあります。
扱いやすい「フタホシコオロギ」、水切れに強い「ヨーロッパイエコオロギ」、とても大きくなる「クロコオロギ」がおすすめです。
餌の頻度は、ベビーからヤングの成長期は毎日食べるだけ与えても良いです。
アダルトに近づくと自然と食欲が落ち、数日おきに一回のペースになります。
レオパに限らず爬虫類は、拒食をする時期があります。
我々人間や犬・猫と違い、毎日ご飯を食べなくても生きていけるため、過度な心配は不要ですが、栄養を溜め込んでいる尻尾の太さを普段からよく観察しておきましょう。
デュビア
アルゼンチンフォレストローチという、南米のゴキブリです。日本のゴキブリと違い、飛ばない、登らない、動き回らない、飼育の容易な餌用昆虫として人気です。
またコオロギと比べて、鳴かないので、うるさくありません。
ミルワーム
ゴミムシダマシの幼虫です。よく海外のブリーダーは、レオパにミルワームを与えています。
コオロギなどに比べて、ピンセットで与えるのは、少し面倒かもしれません。動きが苦手な方は乾燥ミルワームもあります。
レオパのアダルトには小さいため、ジャイアントミルワームもおすすめです。
人工フード
ジェックスのレオパブレンドフードは、ぬるま湯でふやかして与えるタイプのドライペレットです。
アメリカミズアブという昆虫が、47%原料として配合されています。
長期給餌試験から獣医師も推奨している人工フードで、ゴキバンクのレオパにもこれだけで育った個体がいます。
キョーリンから発売されている、ふやかす手間のいらない、ゲル状の「レオパゲル」も人気の商品です。
ミルワームやシルクワームなどの昆虫原料が高配合されています。匂いは少し強めです。
レオパの飼育用具
初めて飼育する方に向けて「これを買っておけば間違いない!」という商品を紹介します。ぜひ参考にしてみて下さい。
ケージ・ヒーター
レオパの隠れ家となるお家です。
脱走のリスクが低い爬虫類ケージを導入して下さい。水槽で飼育する場合は蓋が必要です。
ヒーターは、全体が暑くなりすぎないようにケージの底面積1/3を目安に敷いてください。
床材
こちらの床材は生体が誤食しても体内で吸収されるようです。色味がオシャレでレイアウトが捗ります。
よくレオパを買いに来たお客さんに「この床材の商品名を教えてください」と言われます。
ウェットシェルター
初めて飼育される方は絶対これ使って下さいね!湿度を保ち脱皮不全の予防にも繋がります。
ケージ内にウェットシェルターがあれば、湿度を気にする必要がなくなります。
ベビーは水入れで溺れないように注意が必要です。S・M・Lから成長に合わせたサイズ選びをお願いします。
餌皿・水入れ
ピンセットで活餌を給餌する場合、餌皿は不要かもしれません。水入れに関しても、レオパはウェットシェルターをペロペロしたり、水入れに浸かったりするのでお好みでどうぞ。
レオパのよくある質問
これからレオパを飼育したい、もっとレオパのことを知りたい人に向けて、よくある疑問質問にお答えします。
レオパのオスメスの見分け方
オス

オスには総排泄口の下部にヘミペニスが収納されているため、外部から膨らみが確認できます。また前肛孔と呼ばれるアーチ状の鱗も確認できます。
メス

メスであれば、ヘミペニスの膨らみも、前肛孔の鱗も存在しません。
ベビーからヤングのレオパは、雄雌の正確な判別が難しいで注意して下さい。
飼い主に懐くの?

残念ながら、爬虫類であるレオパは人間に「懐く」ことはありません。しかし「慣れる」ことはあります。
人間が近づいたり、ハンドリングしようとすると暴れるレオパでも、いつか慣れる場合があります。
中には人間に慣れないレオパもいます。その場合は、無理にハンドリングせず、最適な距離感を保った飼育を心掛けて下さい。
また毎日レオパに餌をあげていると、近づくだけで待ちきれない様子でジタバタする可愛い姿を見ることができます。
人工フードだけで育てられる?
前提としてレオパは昆虫食です。最初は人工フードを食べていても、成長に伴い欲しがる餌が変わることもあります。
拒食が始まったとき、コオロギなどの昆虫を飼育する覚悟があるか、よく考えてからレオパをお迎えしましょう。
尻尾を切りますか?
レオパは危険を感じると尻尾を自切します。
カナヘビやニホントカゲが天敵から襲われた時に尻尾を自ら切り離すイメージです。
レオパの尻尾には栄養が蓄えられているので、できるだけ尻尾を切らせないようして下さい。
大きな音を立てたり、乱暴に扱ったり、尻尾に触ったりしない方がいいです。
数ヶ月かけて再生尾と呼ばれる新しい尻尾が生えてきますが、鱗のない滑らかな質感となります。